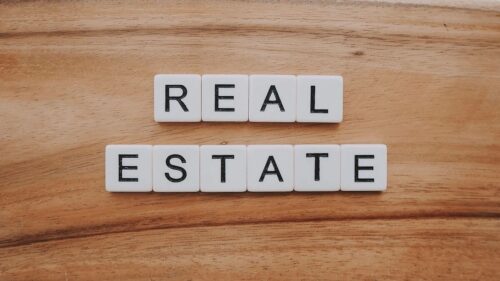宅建の勉強をする際、一番最初に学習する単元です。
不動産を売ったり、貸したりする、会社や人たちが、全員宅建業の免許が必要か?と言うとそうではありません。
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う時に、免許が必要となります。
免許を受けたもののことを宅地建物取引業者、いわゆる宅建業者と言います。
今回は宅建業の定義を学びましょう。
「取引態様の自ら貸借」「不特定多数を相手に反復継続」は、試験で何度も出ている重要ポイントです。
宅地の定義
①今現在、建物がある土地。(登記簿の地目ではなく、現況で判断する)
②建物を建てる目的で取引する土地。(今現在、建物がなくてもよい)
③用途地域内にある土地。(例外:公園・広場・道路・水路・河川は用途地域内でも宅地ではない)
建物の定義
屋根と柱がある工作物。
①一戸建て
②マンションの専有部分
③倉庫
※リゾートクラブ会員権の売買も、建物の売買とみなされます。
取引の定義
取引態様と契約のタイプによって、取引に該当するかが決まる。(〇は取引に該当し、×は該当しない)
| 売買 | 交換 | 貸借 | |
| 自ら当事者 | 〇 | 〇 | × |
| 代理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 媒介 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理→依頼者の代理人として契約
媒介→仲介。契約を結ぶ権限なし
◎取引に該当しないもの
自ら貸借や、自ら転貸借は取引に該当しない。つまり、宅建業法上の規制を受けない。
マンション管理、建築請負、貸ビル業、貸駐車場、賃貸マンション経営も該当しない。
業の定義
不特定多数に反復、または継続して行うこと。
多数でも一定の範囲に限定されている場合は、対象が特定されているので業に該当しない。例)自社の従業員のみ

相手が「公益法人のみ、国その他宅建業法の適用がない者、友人や知人」を対象とする場合は、対象が限定されていないため、業に該当する。

持っている土地を一括で売る場合は、繰り返しや継続して行うわけではないので業に該当しない。
一括して代理・媒介を依頼しても、代理人や宅建業者が不特定多数に反復継続して契約を結ぶと、自ら当事者として「業」を行うことになってしまうので注意。
営利目的の有無は関係ない。学校法人や宗教法人のような公益法人が行う場合も業に該当する。無報酬でも業になる。
破産管財人が、破産財団の換価のため自ら売主となって、宅地建物の取引を反復継続して行うことは業には該当しない。
※ただし、代理・媒介を業として行う者は免許が必要となる。
免許が不要な人・団体
自ら貸借する人、自ら転貸借する人。
マンション管理、建築請負、貸ビル業、貸駐車場、賃貸マンション経営。
国、地方公共団体(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)。
信託会社、信託業務を兼営する金融機関等。
みなし宅建業者。
事務所の定義
商業登記簿に登載されているかどうかは関係ない。
宅建業法上の事務所とは、
①本店(主たる事務所)直接宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいるならば事務所にあたる。
②宅建業を営む支店(従たる事務所)ただし、宅建業を営んでいなければ、事務所としてカウントされない。
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くところ。
ただし、一時的な出張所は含まれない。案内所(モデルルームやイベントのテント)は事務所ではない。
問題に挑戦!
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述は、マルかバツか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
1.Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2.Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。
3.破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
4.不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 宅建業」を御覧ください。
 あこ課長
あこ課長YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。